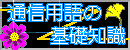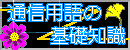阪急電鉄の路線の一つで、京都線の路線の一つであり、盲腸線。
- 総延長: 13.6km
- 軌間: 1435mm軌道(標準軌)
- 駅数: 11駅(起点、終点の駅を含む)
- 単線複線: 全線複線
- 電化区間: 全線電化、架空電車線方式・直流電化1500V
- 閉塞方式: 自動閉塞方式
- 保安装置: (不明)
- 運転速度: 最高80km/h(192km/hBeat)
- 所要時間: 北千里〜天神橋筋六丁目: 26分〜30分程度
- 1921(大正10)年: 十三駅〜淡路駅〜豊津駅(北大阪電気鉄道) 開業
- 1921(大正10)年: 豊津駅〜千里山駅(北大阪電気鉄道) 開業
- 1923(大正12)年: 新京阪鉄道
- 1925(大正14)年: 天神橋駅(現、天神橋筋六丁目駅)〜淡路駅 開業
- 1928(昭和3)年1月: 全線を1500Vに昇圧完了
- 1930(昭和5)年9月: 京阪電気鉄道 千里山線となる
- 1943(昭和18)年10月: 京阪神急行電鉄発足
- 1949(昭和24)年12月: 京阪神急行電鉄 千里山線となる
- 1963(昭和38)年8月: 千里山駅〜新千里山駅(現、南千里駅) が開業
- 1967(昭和42)年3月: 南千里駅〜北千里駅間が開業、千里線に改称
- 1973(昭和48)年4月: 阪急電鉄 千里線となる
- 1992(平成4)年4月1日: 磁気式プリペイドカード「ラガールカード」でストアードフェアカード化開始
- 1996(平成8)年3月20日: スルッとKANSAI導入
- 2004(平成16)年8月1日: PiTaPa導入
- 2013(平成25)年12月21日: 駅ナンバリング導入
列車種別
- 特急 (行楽期のみ運転)
- 準急
- 普通
種別の特徴
準急は、淡路駅から京都本線に、天神橋筋六丁目から地下鉄堺筋線に各々乗り入れる列車である。
堺筋線天下茶屋発の列車は、天神橋筋六丁目から千里線に乗り入れ、千里線内は、柴島駅を通過する。淡路駅からは京都本線に乗り入れて高槻市駅へと向かう。
行楽期のみ運転される特急も、柴島駅を通過する。
淡路駅で京都本線と平面交差しているため、信号待ち停車などが多かった。
2018(平成30)年度末にJR西日本がおおさか東線の開業を予定しており、淡路駅で乗り換え可能とする計画である。
そこで千里線も、柴島駅〜淡路駅〜下新庄駅までを高架化し、京都本線と立体交差化する計画である。
千里線は、北千里駅という中途半端な所で終わっている盲腸線である。
元々の千里線の計画では、南千里駅から北西方向に伸ばして箕面線の桜井駅へと繋げ、千里ニュータウンを貫く鉄道となる予定だった。
しかし千里ニュータウンを造成していた大阪府の妨害があり、結局南千里駅から桜井駅に直結するルートは建設不可能となり実現しなかった。やむを得ず代替路線として、大阪府などと共同出資して北大阪急行電鉄を作り、梅田から千里ニュータウンまでを結ぶ路線が作られた。
そしてこの路線も、計画を変えて北千里駅まで延伸して千里線に改称し、現在に至っている。
このような経緯から、当初は北千里駅から桜井駅へと結ぶ予定で、北千里駅も途中駅の前提で作られていた。しかし冷静になった阪急電鉄、北千里駅からでは桜井駅まで遠いこと、北大阪急行電鉄がある中で桜井駅まで伸ばすメリットが薄れたことなどから意気消沈、遂に延伸されることはなく計画は消滅、今も中途半端な終着駅のままである。
周辺住民はいまも延伸に期待を寄せているとされ、府道119号沿いの北千里駅から北西方向への延伸用の土地もある程度確保されているが、大阪府の財政難などもあり、この土地も徐々に転用が進んでいる。
駅ナンバリングは2013(平成25)年12月21日から実施。
以下、(ラチ内)はラチ内乗り継ぎ可能なことを示し、記述の無いものは全てラチ外乗り継ぎとなるものを示す。
正式な起点は天神橋筋六丁目だが、運行上は北千里駅行きが「上り」、天神橋筋六丁目駅行きが「下り」と逆になっている。
- K11 天神橋筋六丁目駅
- HK-87 柴島駅
- HK-63 淡路駅
- 京都本線 (ラチ内、同一ホーム) (一部直通列車あり)
- HK-88 下新庄駅
- HK-89 吹田駅
- HK-90 豊津駅
- HK-91 関大前駅
- HK-92 千里山駅
- HK-93 南千里駅
- HK-94 山田駅
- HK-95 北千里駅
(未確認)
(未確認)
峠はない。
- 大阪府
- 大阪市(北区 ‐ 東淀川区) ‐ 吹田市
関連するリンク
 えきから時刻表 [阪急]千里線
えきから時刻表 [阪急]千里線 用語の所属
用語の所属

 阪急電鉄
阪急電鉄